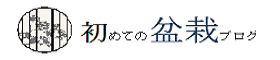ケヤキの育て方

今回は、雑木盆栽で人気樹種のケヤキの育て方をまとめていきたいと思います。
ケヤキは花物や実物盆栽に比べると、見た目がやや地味な印象がありますが、どうして人気樹種なのでしょうか?
ケヤキは街路樹や公園でよく見かける樹です。新緑~紅葉~落葉の葉の変化で四季を感じられること、幹肌がきれいなこと、など特徴があります。
紅葉は赤や黄色に色つきますが、モミジほど綺麗な赤ではなく、イチョウほど目立つ黄色でもありません。しかしそれが逆に、紅葉から落葉する際に郷愁を誘います。
また、ケヤキは箒(ほうき)作りといって、まっすぐな直幹で育てられることが多く、まじめにけなげな、悪く言えば愚直な印象さえあります。
”わびさび”の好きな日本人の琴線に触れる部分が多いのが人気樹種となった理由なのでは、と考えています。
ケヤキ盆栽の増やし方
ケヤキは、実生、挿し木、取り木にて増やすことができます。
おススメは、実生から育てる方法です。
実生から育てる
11月位になると、公園など地植えの大きなケヤキの木から種が採取できます。
11月になると枝の先についている種が土色になってきます。先端の枝ごと、落ちる時期が採取に適した時期になります。地面に落ちた種が、乾かない前に採取してビン(ジャムの空き瓶など)の中に保管します。
公園によっては、採取できないところもあるかと思いますので、くれぐれも採取しても可能なところか確認してから採取してください。
採取した種は、1日ほど水につけ発芽率の高い沈んだ種を取り蒔きにします。(冷蔵庫にビンで保管し春に蒔いても良いのですが、当方は取り蒔きで行っています。)
実生のメリットは、多くの素材を確保することができることです。また、細かな枝を作るためには一年目から芽摘み、葉刈りが必要なので、箒立ちの形を作りやすいです。
実生のデメリットは、思ったほど発芽しないことです。
ケヤキは発芽率のサイクルがあるらしく、発芽しやすい年と発芽しにくい年があります。
水につけ、沈んだ種を蒔いても、ほとんど発芽しないときはがっくりです。
種採取の注意点
種を採取するには実をつけた樹形の良い親木を選ぶことが重要です。

ケヤキは親の性質を受け継ぐので、できるだけ枝葉が左右均等に細かく分かれているものを選びましょう。
また、発芽率を上げるためには、単独で植えられているケヤキではなく近くに数本まとめて植えられているケヤキから種を採取しましょう。
枝が細かく分かれ、小さな葉をつける理想的な箒(ほうき)立ちのケヤキを作るためには、最初の大事な要素となります。
軸切り挿し芽、直根切り
発芽後、しばらくすると十字に葉が出てきます。そのタイミングで軸切り挿し芽または直根切りを行います。

挿し木から育てる
挿し木のメリットは、親木があれば簡単に、挿し穂を複数取れ一度に多くの素材を手にすることができること。実生より早く盆栽として形にすることができることです。
挿し木のデメリットは挿し木は、まっすぐな直幹にするのがやや難しい点があります。
挿し穂自体が曲がっていると、後で幹を真直ぐにするのは困難です。また、挿し木する際に、斜めに切り口を作るため、発根が左右均等になりにくいことが影響しているように思います。
取り木から育てる
ケヤキは、直幹で育てることが多いですが。幹の成長すると腰高の間延びした盆栽になることがあります。
実生の場合、軸切り挿し芽にすれば、ミニ盆栽でも箒立ちにできます。軸切り挿し芽にしていない場合で、腰高になった場合のリカバリーとして取り木を行うことがあります。
取り木のメリットは、切り離す方も元の方も腰の低い盆栽として育てることができる点です。
取り木のデメリットは、取り木が失敗することがあることと、切り離すまで時間がかかることです。
剪定、芽摘み、葉刈り
葉物盆栽として、きれいな樹形を整えるためには、剪定、芽摘み、葉刈りの作業が必要です。
剪定
ケヤキは春から枝が旺盛に伸びてきます。
生長期の剪定
4~5月位~夏の間に伸びた徒長枝はそのたびに剪定するようにします。
全体的に見て、左右均等に丸みを帯びた樹形にしていきます。
休眠期の剪定
葉がついている秋までは、枝の正確な形は分かりにくいですが、12月になり落葉すれば、枝の輪郭がはっきりわかります。
この時期に、樹全体の枝の輪郭を丸くすることで、成長期の剪定で切りすぎることなく正確に行うことができます。
芽摘み
芽摘みは、4月になり新芽が出て切るころから、夏の間に新芽の先端を手で摘み取る作業になります。
芽摘みを行うことで、樹形が保たれ、細かな枝葉を作ることができます。
葉刈り
6月に葉がしっかりついてきたら、葉刈りを行い小枝を作ります。
葉は、樹勢に応じて6割~9割ハサミで切り取ります。
切りすぎに思えても、樹勢の良い樹はひと月もすれば徐々に新しい葉をつけてきます。
植え替え
植え替えは2月下旬から3月上旬に行います。
頻度は1~2年に一度ですが、水遣りの際、鉢の底から水が流れないようなら、詰まっているので植え替えた方が良いです。
ケヤキは初めは、深い鉢で育てることで、幹も太りますが、細かな枝を作るために、実生で4~5年以降は浅めの鉢に移していきます。
浅い鉢に移すためには、植え替えのたびに、太い根は切り細かな根を作る必要があります。
全体の根の長さも1/2~1/3程度に切り詰めて、植え替えます。
針金掛け
ケヤキの針金掛けは、休眠期(12~1月)に行います。
目的はきれいな箒作りのために、枝を外側に開いたり、枝の間隔を調整するために行います。
そのため針金掛けが必要なのはある程度、育成したケヤキです。
逆に幼木の間は、休眠期は、紐などで枝をまとめて縛り、広がりすぎないようにします。
水遣り、肥料
3~4月は毎日一度、5~9月は毎日朝夕2回たっぷりと、10月~11月は毎日一度、12~2月は2日に一回程度水遣りを行います。
特に7~8月は水切れを起こさないよう注意が必要です。
肥料は、固形の油粕の置き肥を生長期に月1の頻度で行います。
用土
用土は、幼木の間は小粒の赤玉土で良いかと思います。
その後は、桐生砂などを1~2割、腐葉土を1割程度成長に合わせて混ぜ込んでいきます。
消毒
ケヤキにはアブラムシが付きやすいとされています。スス病が発生し枯れることもあるので、適期的な消毒作業は重要です。マラソン、スミオチンだけでなく持続性のあるオルトランが良いとされています。